一日の何処かに必ずただ無言で座り込んで死に掛けているだけの時間があるのだが、同様に公園のベンチで死に掛けていた或る日、大きな犬が真っ直ぐ私に寄って来た。私は警戒するのも忘れて、眼を細めて其の顔付きを窺った。ゴールデンレトリバーの目の、どうしてあんなに優しいのか。薄暗い処の無いひたすら開け放した興味だけを湛えて私を見上げるから、虚無の鉛で重く沈んでいた背中はふわりとベンチから離れたのである。彼女か、彼か、差し出された指から膝頭から足元へ、丹念に匂いを嗅いで、何時迄も新鮮に空気を交換している。どんな会話よりも、本当に私を知りたいと思ってくれている──と感じた。勤務の中途、誰に何を言われたわけでも無いのにどうしても遣り切れなくなり、休憩中に人間の群れを抜け出した先で、思いもよらず純粋の興味と関わり合って私は深く救われたのであった。人間は空疎で姑息な定型確認に慣れ過ぎて、其の儀礼の履行を本当の交友だと思い込んでいるが、獣達が我々に向けるのは本来的な関わり合いだ。自分にとって私がどんな存在かを、真摯に知ろうとするのである。其の純粋さは己に向く分だけ、外部にも純粋だ。
「ごめんなさいね。」頭上から人間の声がした。途端に身体が強張る。見られていたのだ!と思った。人が私を外界として認識していて、何かしらの解釈をされているのだ。私は犬から視線を離す事は無かった。婦人は私が一言も返さないし目すら合わせないのを、何とも思わない風にーー其れくらい全ては一瞬の事だったのだーー通り過ぎて行った。犬もまた、軽くリードを引かれれば一瞬で興味は他に移ったようだった。
私が思った事は二つあった。一つは本当に人に”解釈”される事が恐ろしいという事。もう一つは、私は初対面でも犬相手であればあんな風に自然に、実に本来的な交友を持てるのだという事である。後者が私は嬉しかった。ベンチを後にして職場へ戻る。決して心が癒えたからではない。休憩時間が終わりかけていたのである。希望よりも諦めが、私を幾度も救ってきた。
人間社会で生きられない事は、世界から拒絶される事では決して無い。
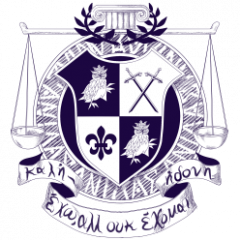
 本来的交流
本来的交流