動物と生活を共にするという事は、我々人類に多くの発見を与え得る。其の中でも、猫は格別素晴らしい。生への尊い利己主義、其の偽り無い美しさに、私は常日頃打ちのめされる気がする。己を脅かさぬ事象──因みに、世界の大半が其れである──に対しては超然とした無関心を魅せながら、彼等が唯一従ずるところの《己が忌避感》に於いては稲光の如き嚇怒の閃きを見せる。生命の焦点、唯己にこそ在れかし。嘘を吐かぬ爪が私を傷付ける時、澄み切る野性の気高さに触れる崇高を確かに感じる。
さて我が家に居る格別の獣も、仔猫時分とは随分に顔付きを変化させて、今や一角に猫らしい魔術的性質を備え出した。玩具を投げれば取って戻るという犬の様な性格は変わらないが、少しばかり通せん坊をしただけでも赤口で威嚇する処などは、矢張り此の種族特有の帝王學を感じさせる。従者たる私は大人しく首を垂れて王侯貴族を御通しするのである。
そうして下らなく生活する内に気付いた猫の習性には愛おしい物が書き尽くせぬ数だけ在るのだが、その中でも一つ、風の匂いを嗅ぐ仕草は、胸が締め付けられる程に美しいものである。我が家の猫に限らない事と思うが、風が吹き付けてくると猫は少し驚いたように宙空を僅か見上げて、熱心に鼻をひくひくさせる。髭を風に揺らしながら、真剣に便りを探る。窓を開けた時もそうであるし、ドライヤーの風がかかった時もそうである。春の夕暮れ、露台の木造りの椅子で膝に抱えた私の猫が、金星の瞳と茶色い毛並み、そして揺れる細い髭を夕陽に煌めかせながら、耳を欹てて不思議そうに風を嗅ぐ時、「嗚呼こんなにも繊細な世界との関わり方は他に無い」と途方も無く思う。嘘偽りの無い世界への興味、太初の神話が産まれた理由そのものが、眼前に息付く様に感じる。科学の根源すら、自然神学に他ならないのだ。自然を知ろうとする事は即ち自然への愛しみだ。だから私は其れが堪らなく好きである。
動物と生活を共にするという事は、我々人類に多くの発見を与え得る。そして私の場合、取り分け美に於いて、計り知れない発見を続けている。
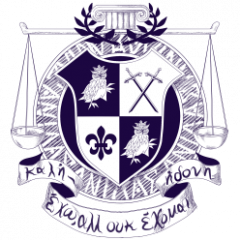
 猫の愛おしい習性の一つ
猫の愛おしい習性の一つ