生命の精神的側面が永らく彼岸にある。肉体を死の深淵へと道連れにしようとぐらりと体重を掛けてくる時もあれば、気紛れに大人しく、静謐な安らぎを装う時も有る。然し兎に角、自暴自棄の、どちらに転ぶか予測させない足運びで、悪戯に生死の縁を歩き続けているのである。私はそんな彼に振り回されて明くる日は自棄に笑い、明くる日は悲嘆に暮れ、明くる日は突然に遠出し、明くる日は寝台からも出られない。精神科の寄越す眠り薬では、彼の遊歩それ自体を止める事など出来はしまい。
そんな予測不可能性の苦悶を秘める蛇行を彷徨う中、本邦に終に“秋”が来たのである。此れは私にとって悲観と孤独の緩む事実であった。惑星から寄せられた懐かしい同情であった。秋は微睡みの刻、活動と休眠の間
。不安定な私が何方に有っても赦される季節が存在した事を思い出したのである。不可思議ながら、幾度巡っても、季節には慣れ飽くことがない。暑さも、寒さも、匂いも、光も、自分の記憶機構の欠陥を疑う程に、何時も白紙に忘れ去っている。こんなに暑かったであろうか、こんなに寒かったであろうか──此の程度の愚かな吃驚を順に循環している。季節の齎す物は一種の神性そのものであり、記憶出来る類の物では無く、必ず忘却されなければいけない物なのでは無いかとすら、私には思われるのである。午後三時に既に洛陽の煌めきを纏う陽射しを窓枠の端に見た時、私は其れが当然という様に、一冊の本を携えて家を出た。子供連れと犬連れが憩う健康的な自然公園の中で、此の身に馴染んだ疎外を掌で転がしながら、日向のベンチに腰を掛ける。持って出たのは『西洋近代詩人集』であった。
詩集は優しい。文芸作品でありながら、読む事を強要しない。どこから読んでも良いし、読み飛ばしても良い、理解しなくて良いし、読んだ傍から忘れて良い。只邂逅を待つのだ。今此の瞬間、私の瀕死の精神を電光の如く射抜く、時空だに重ならぬ誰かの遺した言葉一つを。何処に在るかも、本当に在るかも分からない其れを待ちながら、私は煌めきを増す陽射しの作る陰翳に古い紙の質感を増した頁を、指先で慈しむ様に捲る。喧騒は確と耳に届きながら邪魔では無い。樺色の投射さるる立木の遥か高くから団栗が、道中幾つかの枝にかつんかつんとぶつかりながら、落葉の地表へ軽やかに落ちた。
仏蘭西の、英國の、獨逸の、南欧の詩篇の幾つかで、私はたった一行、たった一つの言の葉達と巡り逢う。如何して日本に居る私が今此の言葉と巡り逢ったのか、果てしない摂理の連鎖に眩暈を覚える程の思いに駆られながら。きっと忘れる此の温度、此の匂い。一回性こそが季節の持つ神性の源だと云うならば、人は何度でも忘れて、何度でも巡り逢おう。
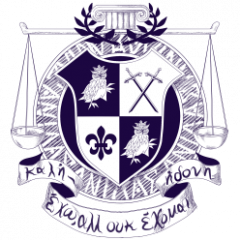
 秋と詩集に於ける赦し
秋と詩集に於ける赦し