人情味に行き当たる日だった。昼過ぎ入った定食屋で、それらしく白い三角巾・エプロンをした大将と、カウンター越しに荷物も下ろさず緑鮮やかなカーディガンという格好の母親が、何やら言い合いをしているのに出会した。休み中の子供達の面倒を見切れない、と言う様な話らしく、大将も私達の注文を聞きながらかなりしっかりと「それは困る」と主張を返していた。直ぐに母も強い意志で返すが、しかし注文を聞くや真っ先に動いたのも母で、嘗ては主として此の店を切り盛りした過去を感じさせた。普段着のまま厨房の豚汁をお玉で掬う母の背中に何やら懐古的な暖かみを感じていると、「そっちのお玉じゃない」などと、また別の火種が生まれる。あくまで当人らにとって此れは真剣な主張のぶつかり合いであって、謂うなれば正当に”喧嘩”だ。ただやはり真に他者から見ると、生活の歴史が其処には滲む。一貫して大将の母への物言いは”息子”的で、面食らう程に幼い気がした。対して母には何処か冷静な部分があり、然も泰然として、客を含めて自分の都合に呑み込む事を厭わない大きさを持っていた。それは年を経て、迷惑をかける・かけられる人間関係のどちらの側も散々やって来た古老特有の大きさだった。
店を出て、バスに乗る。出発間際、「私、何処々に住んでる何々と言いますが、私のアパートの目の前に停まるのはどれですか?」とどうやら存在しないらしい路線を尋ねてくる老爺に一生懸命その不在を回答する二十代の男性運転手という、これまた人情味のあるやり取りがあった。そして暫く走った後、可怪しな時機にピンポン、と降車ボタンが押された。何かの弾みで降車ボタンを誤って押した事は、おそらく誰にでもある。私にもあった。にも関わらず、後方から聞こえた男性の声は以下だった。
「すみません、間違えてボタンを押してしまいました。今のは撤回します。」
一言一句正しく、此の様に彼は言ったのであった。此処から見える彼の愚直な半生よ!彼と云う人はこんな場合にも、斯う伝えるのだ。
昭和に生きた事が無く、東京生まれ東京育ちで、特に幼稚園から私立に通った”地元を持たない”私にとって、他人の生活は見えない事が当たり前だ。然し今日の様にふと他人様の、高尚さなど何処にも無いが故に尊い生活風景や、染み付いた其の人らしさを目の当たりにする事があると、温もりなのか、安堵なのか、訳も分からない果てしない愛おしさを感じる。誰に教えられたのでも無い、人間の生への讃歌に似た異様に壮大で肯定的な気分が私の中に産まれる。人間が努めて人間として生きている姿というのは、システム化された現代社会の中で右往左往する私を励ます様に、寄り添ってくれるのだった。
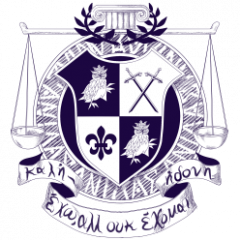
 喧嘩に励まされる
喧嘩に励まされる