既に一月も前の事になる。弐阡弐拾年皐月第六の日は、凄まじい嵐の夜であった。其の時私は、全ての人工的な音を断って部屋を暗闇にし、荒れ狂う雨風を厭わず窓を開け放って、寝台の上に膝を抱えて座っていたのである。街灯に因って見える全ての金属が不気味に光を放つのに怯え、漂い迫る雨の臭いを肺一杯に吸う。只ならぬ緊迫と興奮に眼は前髪の下、見開かれた侭で弱者相応しく潤う。私は或る物を待っていた。
刹那、天空を疾り渡りし閃光。驚愕に喉が引き攣る。予兆を持たぬ威光に肝が潰れる。瞬く間に闇に退き戻された森羅万象が重苦しく怖ろしい静寂を守った。嗚呼今に昏い雨音の中を”遣って来る”。光速を追い、凄まじき速さで我々の元へ襲い来る者が”在る”。叫び出しそうな狂喜が膨張して声帯を食い破りそうになるも大いなる自然達が然うであるように私もまた必死に息を潜めた。
軈て、時が来た。ゴゴ………と、重く垂れ込める雲の上から現世ならざる存在の吐息の如き音が、我々を怖ろしい殺意で見下ろした。原始的な畏怖が私の霊を隅々まで満たした。戒めの轟きが其の余りの忿怒で揺らぐかの様に、不規則に、人間的に唸り続ける。法悦極まる嘆息が漏れ出づる。先史から死せる者の絶対的支配者たる、全天を支配せし彼の悠久の”聖性”が、轟音を従え人類を裁きに来たのだ!
暫く在って、終に”聖性”は去った。左手にずっと握っていた切子のグラスを擡げ、息継ぎする様に酒を飲むと、聖戦の勝利に在って捧げられるべき敬虔清貧なる美酒の鋭さが感ぜられた。恍惚の余韻に酒精の齎す怠惰な空虚が織り混ざって、古代神話の最高神が必ず天候神であり、雷霆を司る存在とされた事が朦朧と思い出される。古代人に神の実在を信じさせたスペクタクルが我々の眼前に今猶お悠然と在り続け、変わらぬ怖ろしさで以って経験されるというのは、果て何と浪漫的な事であろうか?
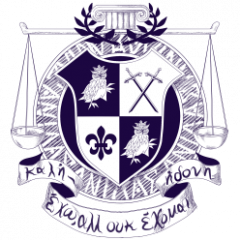
 雷を肴に酒を飲む
雷を肴に酒を飲む